外車のタイヤ交換の基礎知識|タイヤを外す前に知っておこう!
外車のタイヤ交換と国産車のタイヤ交換の決定的な違いは「ボルト」で止めてあることです。
サイズが外国仕様…ではなくて
外車のボルトは車側から出ていない!
つまり、車側には「穴」があるだけで、ホイール側からボルトで締め付けてあるのです!

…それがなにか?
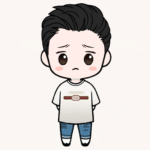
タイヤ交換が難しくなるんだ!
必要な工具もちょっと違うよ!
外車のタイヤは外側からボルトで締め付けてある

ホイールの穴になにか見えますか?
国産車なら「袋ナット」がピカッと光って見えてるはずです。
こういうやつです↓
ところが外車は…
ただのボルトなんです!

国産車とは違うので、外車のタイヤ交換作業にはちょっとしたコツと、便利グッズがあります。
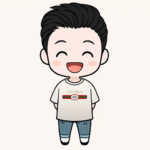
今回は作業に必要な知識と道具を実況風に紹介します!
タイヤ交換、外車と国産車の違いで起こる悲劇とは?
国産車の場合、タイヤを外すときに回すのは「ナット」ですよね。
袋ナットというものを取り外すと、車側からネジが突き出しているのが見える…これが常識です。
アルミホイールでも鉄製のホイール(通称「鉄チン」)でも、形状は違えど「ナット」を外します。
鉄製ホイールは貫通型のナットですが、アルミホイール用の袋ナット同様、車体側から出ているボルトに締め付けていくのが国産車の常識です。

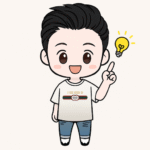
ところが、外国車では反対に「ボルト」でホイールを外から締め付けています。

これを知らないで作業を始めると、ボルトを抜いた瞬間にタイヤがズドンと落ちて驚くことに。
場合によっては怪我をすることもあります。
外車のタイヤ外し作業の注意点|ボルトを外したらタイヤが落ちる
国産タイヤは、ナットを外しても車体からボルトが出ています。
ジャッキアップしたホイールのナットを外しても、車から出ているボルトに引っかかるので落ちることはありません。
ところが、外車の場合はボルトを抜くために何も支えるものがなくタイヤがズドンと落ちてしまいます。
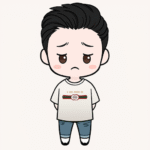
引っかかったとしても、ボルト穴とボルトに不要な負荷がかかります。
作業のときは、タイヤを支えて落ちないように保持し、ボルトを抜く必要があります!
タイヤを保持しないまま無理やりボルトを引き抜くと、タイヤとホイールの重量がボルトのネジ山にかかってしまい、最悪の場合はボルトの山がゆがんでしまいます。
ネジ山が歪んでしまったら取り付けるときに車体側のネジ山の一部を潰してしまうこともあるため、新しいボルトを買わなくてはならなくなることも。
面倒でも、タイヤがボルトにぶら下がってしまうような外し方はせず、タイヤを保持して外しましょう!
具体的なタイヤの保持方法としては、
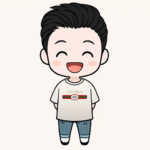
僕の場合は、3つ目の「自分の太ももにタイヤを乗せて支える」スタイルです。
一人でできるし、ツールも不要。
とにかく、国産車のように車体に引っかかっているホイールを引き抜く感じではないことに注意してください!
外車のタイヤ取付け作業の注意点
今度は取り付けるときの難題です!
国産車なら、ボルトにホイールの穴がハマるように差し込む感じですよね。
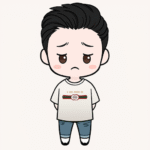
ところが、外車のタイヤは「穴と穴を合わせたうえでボルトを差す」といった、ありえないワザが必要です。
外したときと同じ要領で太ももに乗せるんですが、ホイール穴と車体側の穴を合わせるのはめちゃくちゃ難しい!
はじめはなんとかやってましたが、翌日から筋肉痛になりました。
真夏だったらズボンが汗で違う色になります!
タイヤ交換に使う工具|最低限のツール5選
ここでタイヤ交換を自分でするときに必要な工具一式をおさらい。
すでに持っている人はすっ飛ばして先に進んでください。
ジャッキ|おすすめは2tの油圧ジャッキ
車に標準でついているジャッキは、緊急時につくものと割り切りましょう。
作業効率が悪い上に、壊してしまったら緊急時に使えません。
自宅でタイヤ交換するときは、時間と体力を消耗しない油圧ジャッキがおすすめです。
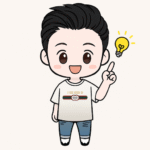
エアロパーツがついていたり車高を下げているときは「ローダウン」と書いてあるものを購入します。目安は2トン以上のものがおすすめです。
タイヤ交換を車屋さんにお願いすると2万円前後必要。
夏・冬の2回は交換するので、2万円のものを買っても半年で元が取れます。
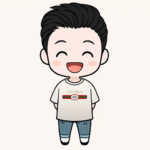
僕は2万円のものを5年以上使っています。
トルクレンチ|デジタルじゃなくていい
ボルトの締め付けには、車ごとに強さが決まっています。
- 弱すぎるとボルトがゆるんで危険
- 強すぎるとネジ山を潰して危険
タイヤ締付けの強さは「トルク」と表現していて、単位は「N・m(ニュートン・メートル)」です。
以前は「kgf」という単位が使われていましたが、国際規格が変わりました。数字はほぼ同じなので、単位が違っても数字さえ覚えておけばオッケーです。
メーカー発表のタイヤボルト締め付けトルク値をいくつかご紹介。
| 車種 | メーカー規定トルク |
|---|---|
| BMW 218シリーズ F45など | 140N・m |
| アルファード(30系以前) | 103N・m |
| アルファード(40系以降) | 140N・m |
| N-BOX | 108N・m |
自分の車のタイヤボルト締め付けトルクは取扱説明書にも書かれているし、ネットでも…
「セレナ タイヤ トルク」
みたいに検索すれば出てきます。
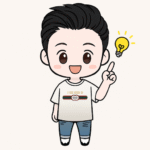
締め付けトルクがわかる工具を使って締め付けます。
「トルクレンチ」です。
トルクレンチには「機械式」と「デジタル式」の2種類があります。
おすすめは安くてシンプル、タフな機械式です。
機械式トルクレンチ|タフでシンプルさがおすすめポイント
メモリを締め付けたい数字に合わせて使うだけのシンプル構造。
目的の締め付け具合になったら、工具の中のバネが「カキン!」と音を鳴らして教えてくれます。
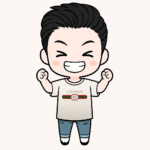
僕は20年以上、機械式しか使っていません。とにかくシンプルでタフ
デジタル式トルクレンチ|正確だけどプロ向け
デジタルメーターが付いているタイプのトルクレンチです。
正直、タイヤ交換用にはここまでの精密さは不要。
それに、DIYでタイヤ交換するのは青空の下ですよね。整備工場のような雨風しのげる場所じゃないし、工具も専用ラックにしまったりしません。
一度使ったことありますが、2回めに使おうとしたら壊れてました。
自宅に整備ガレージがある人や、精密に締め付けたい人以外は全く不要です!
ラチェットレンチ|十字レンチでもOK
規定の締付けは最後の工程ですが、普通に回すときは軽いラチェットレンチが便利です。
先端のソケットは付け替え自由なので、タイヤ交換だけでなく別の場所の整備や、自転車の整備や、家電や家具の組み立てなどでも使えます。
長さが色々あるので、使いやすそうな20cm前後のものを1本持っておくと便利。
安物でいいけど、エクステンションバーがついているセットを選んでおくと尚良しです。
エクステンションバーは別売りだとこんな感じです。
定番の潤滑油|クレ556
ホームセンターならどこでも売ってると思います。
いわゆる潤滑油で、サビ落とし効果もあります。
タイヤ交換作業ではじめに使うのがこれ。
作業開始前に、すべてのタイヤボルトの根本に吹きかけておきます。
5分待ったら、作業開始。
ニトリル手袋|100円ショップのものでもいい
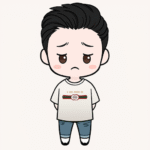
作業のコツは「絶対にケガをしないこと」です!
すり傷、切り傷、肌荒れなんて素人では恥ずかしいだけです。何より怪我をするだけで作業時間が大幅に伸びてしまいます。
絶対に手袋して作業してください!
できれば軍手はやめといたほうがいいです。
結局、滑ったり油まみれになったりするだけなので!
外車のタイヤ交換の便利ツール|一度使ったらやめられない
次に、外車のタイヤ交換作業をスピーディかつ安全にできるツールを2つ紹介。
数千円で超時短になるので、
「なんでもっと早く買わなかったんだろう」
と思います、ぼくはそうでした。
国産車のように、「車側に棒を仮につけておく」ガイドバー
国産車なら、車体側から出ているボルトを、タイヤホイールの穴に通すだけ。
しかし、外車の場合、タイヤを取り付けるときは、車体のボルト穴とタイヤのボルト穴をぴったりあわせる必要があります。
重いタイヤを、宙に浮かせながら車の穴と同じ位置に合わせて…ボルトを仮締めする!
さすがにこれは難しい!
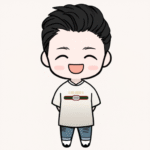
だいたい困っていることは、専用ツールで解決できます。毎年2回使うのに2千円程度の価格帯。ぜひ使うべきです。
BMWなど、ジャッキポイントの補助ゴム「ジャッキパッド」
外車のタイヤ交換のちょっとしたコツ
まとめ|外車のタイヤ交換はツールがあればすぐ終わる
正直、ぼくも初めて外車のタイヤ交換をしたときは、ふとももでタイヤを支えていたせいで筋肉痛になりました。
ガイドボルトはYouTubeなどの動画で見たことあったんですが、買わなかったんです。
でも、買わないと損です。
ほんの数千円で、作業時間は半分!
筋肉痛なし!
なによりも安全だし、ガイドボルトも多分10年は使えます。
悪いこと言いません、あなたが外車のタイヤ交換を自分でするなら、絶対にガイドボルトは買ったほうがいいです!
めちゃめちゃ楽チンですよ!
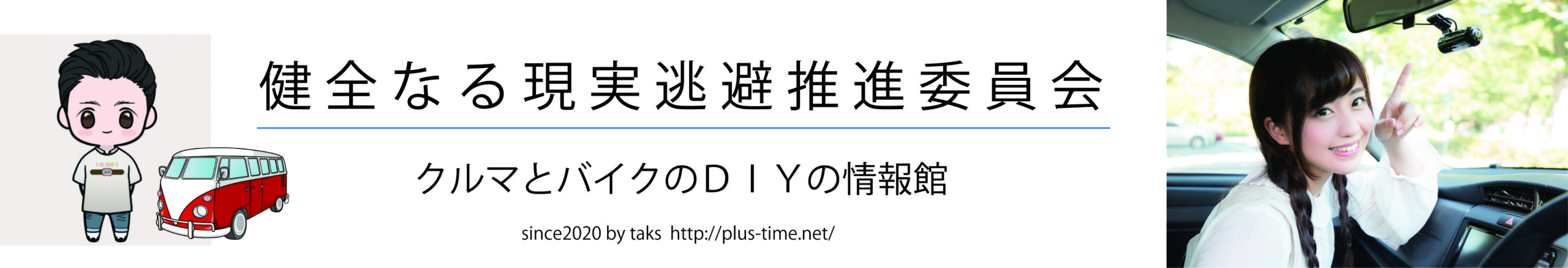








コメント